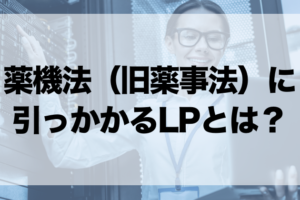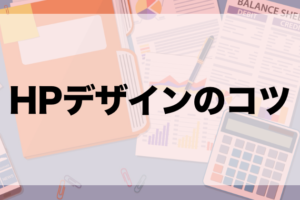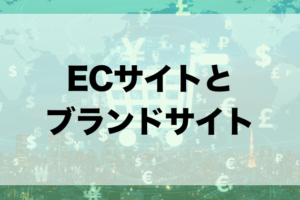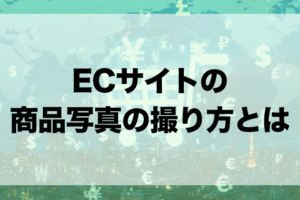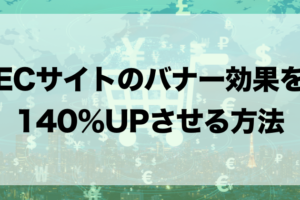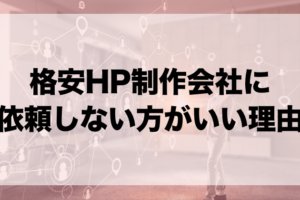最近では集客にオウンドメディアを企業が増えています。オウンドメディアとは企業が自ら所有し運営する媒体ですが、従来のホームページとの違いがわからないという人もまだまだ多いです。
そこで今回はオウンドメディアとホームページの違いがわからない人に向けてそれぞれにどんな違いがあるのか、オウンドメディアが注目されている理由や制作する際のポイントについて解説をしていきます。
ぜひそれぞれのメディアの特徴を理解し、正しい目的に沿って活用をしていきましょう。
この記事を読んだらわかること
・オウンドメディアとブログの違い
・オウンドメディアが注目される理由
・オウンドメディアを制作する際のポイント
・それぞれのメディアの特徴を理解し、目的に応じた使い分けが大切
オウンドメディアはSEOが重要で、上位表示されなければコンテンツを配信しても意味がありません。我々は自社でもオウンドメディアを運用することでそのノウハウを蓄積し、SEOに強いオウンドメディアの戦略から運用まで提案できますので、お気軽にご相談ください!


オウンドメディアとホームページの違い
オウンドメディアは簡単に言うと企業が自ら所有する媒体となり、広義で言えばホームページもオウンドメディアの1つとなってしまいます。
しかし、一般的に使われるオウンドメディアはもっと狭い意味合いのもので、ホームページとは異なる媒体です。そのため、ここでは先にそれぞれの定義を理解し、それぞれの違いを理解していきましょう。
ホームページとは?
まずホームページとは主に消費者に向けて会社概要やサービス、事業内容に関する情報を掲載したページを1つのサイトとしてまとめたものです。
ホームページの目的は企業に関する情報を知りたいユーザーに答えを提示し、問い合わせや購入といった行動から受注や売上を発生させることになります。
また、ユーザーが企業のホームページを訪問する時は、検索キーワードに「会社名」を入れるため、宣伝や口コミで商品を知った、以前サービスを利用したなど既に企業を知っているケースがほとんどです。
裏を返せば企業の名前さえ知らない人が訪問するケースは多くありません。つまり、自社のことを知っていたり、商品やサービスに興味がある人が訪れ、情報収集や問い合わせをする場合に利用されるのがホームページです。
ホームページについてもう少し細かく知りたい方は以下の記事を参照してください。
参考:【ホームページとは?】目的や用途、制作の際に重要な5つのポイント解説
オウンドメディアとは?
オウンドメディアは企業が役に立つ情報やコンテンツを配信していく媒体で、言わば企業が運営するブログのようなものです。主な目的は情報の発信によってユーザーに自社を知ってもらい、ホームページを訪れてもらうことになります。
オウンドメディアは情報の配信を通してこれまで自社を知らなかった人たちに対してアピールを行い、興味を持ったユーザーに商品や事業内容などに対する理解を深めてもらう媒体です。
他にも企業のイメージを伝えるブランディングや商品やサービスのマーケティングなどでも利用されますが、総じて「集客」こそが主な役割となります。
オウンドメディアへの理解を深めたい方は以下の記事がおすすめです。
参考:【オウンドメディアとは?】制作の目的やメリット、構築に必要な要素を解説
オウンドメディアとホームページの違い【まとめ】
オウンドメディアとホームページの違いをまとめると以下のようになります。
・オウンドメディアはユーザーの役立つ情報を提供して「集客」につなげる媒体
・ホームページは企業に関する情報を提供して問い合わせや購入など「セールス」につなげる媒体
ただ、この2つはそれぞれ独立しているわけではなく、ホームページというツリーにオウンドメディアという枝葉がぶら下がっているというイメージで、お互いに作用し合う媒体です。
オウンドメディアとブログの違い
オウンドメディアとホームページの違いが理解できたところで、次はオウンドメディアとブログの違いを解説していきます。
どちらも情報を発信するという意味では同じ媒体のように思われますが、ブログは簡単に言えば日記のようなもので「いつ、どこで、何をした」などの日常の出来事や個人的な感想、意見などを述べる場です。
それに対してオウンドメディアは日常的な事柄は掲載せず、ユーザーの抱えている悩みや問題を解決するために役立つ情報や商品、サービスを紹介するのが主な役割です。
これはオウンドメディアの集客という目的を考えるとわかりやすいですが、企業が運営するメディアで担当者が昨日どこで何をしたかという情報を発信してもユーザーは興味を示さず、当然集客にもつながりません。
しかし、ユーザーが困っている内容や知りたいであろう事柄を推測し、それに沿った記事を作ればユーザーをオウンドメディアへ誘導できます。
こうした明確な違いがあるので、オウンドメディアを運営する際はブログのような内容にならないよう注意が必要です。
オウンドメディアが注目される理由とは?
オウンドメディアは2010年から2011年を堺に広まりだした媒体で、その注目度は年々高まっています。それ以前まで主流だったホームページから一変して今では大半の企業が何かしらのメディアを運営しているほどの人気です。
こうした集客媒体の移り変わりには以下のような理由があります。
・従来の広告手法が限界
・検索エンジンの対策
・コンテンツを資産化できる
・アクセス数の増加を見込める
ここではそれぞれの理由を詳しく解説していきます。
従来の広告手法が限界
SNSの普及によって企業や個人を問わず誰もが自由に情報を発信できるようになりましたが、それによって企業の広告は埋もれてしまいました。
それと同時に多くの企業が広告を掲載しているために飽和状態であり、ユーザーも多すぎる広告を毛嫌いするようになったため、たとえどんなに有益な情報を掲載したとしても広告と判断されれば読んでもらえないのが現状です。
こうした背景から従来の広告を使った集客方法は費用対効果が低下したため、企業は別な方法での集客を余儀なくされました。
検索エンジンの対策
オウンドメディアが普及する以前は検索エンジンのアルゴリズムも単純だったので、被リンクを大量に設定したり多くしたり、キーワード対策をするといった対策だけでも上位表示が狙えました。
しかし、オウンドメディアを利用する企業が増え、記事の数も増えてくると、より良いサイトをユーザーに閲覧させるためにアルゴリズムは複雑化し、現在のGoogleはドメインの価値を重視するようになっています。
詳細の説明は省きますが、従来の被リンクなどに加えてページ数や質など一定の基準を満たしたコンテンツを配信することでドメインの価値が上がり、検索エンジンに評価されて上位表示されるという仕組みです。
コンテンツを資産化できる
オウンドメディアはよく不動産に例えられますが、コンテンツの累積によって集客効果が高まり売上も増加していくので、サイト自体の資産価値も高くなっていきます。
また、一定のアクセスがあればサイト自体の売却も可能で、育てたオウンドメディアを大手企業に数億円で売るというビジネスも存在するほど価値のある媒体です。
従来の広告をかけて集客をするメディアは、一時的なアクセスのために毎回お金をかける必要がありましたが、オウンドメディアはGoogleから評価を受けるとお金をかけずに継続的に集客ができます。
広告の効果が低下している現状もあるので、企業が資産になるオウンドメディアを運営したいと思うのは自然の流れと言えるでしょう。
アクセス数の増加を見込める
オウンドメディアはコンテンツの増加によって集客力が向上しますし、Googleも質の高い記事を上位表示させるという仕様になっているため、ペナルティを受けるような行為さえしなければアクセス数は増やし続けられます。
また、前述したようにオウンドメディアはホームページへ導くという役割を持つので、アクセスの増加によってホームページへの流入、そしてセールスの機会も増えていきます。
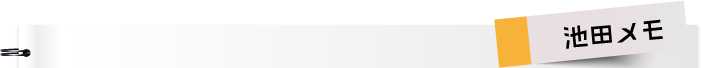

初期費用や成果が出るまでは時間がかかるものの、Webマーケティングの中でも費用対効果が高い施策です。

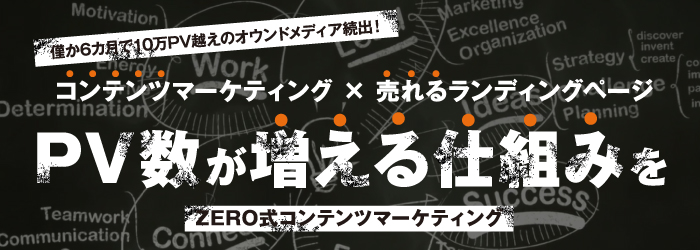
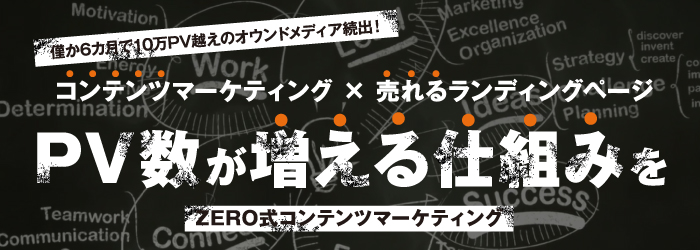 ZERO式オウンドメディア構築・支援はこちら
ZERO式オウンドメディア構築・支援はこちら
オウンドメディアを制作するポイント
オウンドメディアがどんなものかわかってきたところで、実際に制作する際に注意すべきポイントも把握しておきましょう。これを無視して制作するとオウンドメディアの効果は発揮されず、無駄に終わる可能性が高くなります。
ぜひ以下で紹介する4つのポイントをチェックしてみてください。
・オウンドメディアを制作する目的、コンテプトを定義する
・ユーザー視点に立ったサイトを意識する
・各ページの検索ワードを決める
・導線を正しく設計する
オウンドメディアを制作する目的、コンテプトを定義する
まずはオウンドメディアを制作する目的やコンセプトをしっかりと決めるところからスタートします。なぜなら人事採用につなげるために制作する場合と商品の認知ではアプローチの方法が異なるからです。
そのため、まずはユーザーにこのオウンドメディアがどんな情報を発信するものなのかを明確にしなければいけません。また、目的を設定すると制作から運営まで1本の軸ができますし、社員同士の認識のズレを解消できます。
軸がないメディアは運営をしていくと本来の目的を見失ってしまい、効果の上がらないものになってしまうので注意しましょう。
オウンドメディアのコンセプトについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。
参考:オウンドメディアにコンセプトは必要か?設計方法や成功事例を紹介
ユーザー視点に立ったサイトを意識する
オウンドメディアで配信する記事はユーザーが知りたい、悩んでいる事柄に沿ったものにしなければ興味を持ってもらえないので、常にユーザーの視点に立って運営をしなければなりません。
また、ユーザーは広告を毛嫌いするようになっているので、押し売り営業のようになってしまうとページの離脱に繋がったり、悪評が広まるなどの悪影響をもたらします。
オウンドメディアの目的にマッチするターゲットが、どんなサイトであれば来てくれるのか、どんな記事を欲しているのかを考えるようにしましょう。
各ページの検索ワードを決める
オウンドメディアでコンテンツを配信する際に、流入につなげるためのキーワードを各ページに配置する必要があります。
このサイトも「オウンドメディア ホームページ 違い」というキーワードで探した結果たどり着いたと思いますが、ユーザーは常にこうした検索によってオウンドメディアへ到達するので、キーワードの選定は重要です。
ターゲットとするユーザーが知りたい情報からキーワードを把握し、さらにツールを使って関連する検索ワードをあぶり出し、コンテンツへ反映させましょう。
導線を正しく設計する
オウンドメディアはボランティアサイトではないので、有益な情報を発信するだけで終わらせず、ゴールへ到達するための導線の設定が重要です。
例えばゴールが資料請求をしてもらうことであれば資料請求を促すボタンの設置が必要ですし、ホームページへの誘導であればリンクを設置しなければいけません。
また、設置する場所も重要で、資料請求のボタンが記事の最後にある場合と導入の直下にある場合とではコンバージョン率に大きな差が生まれます。
他にもボタンではなくアンカーテキストリンクの方が、クリックされやすいというデータもあるので、自社のターゲットとするユーザーにはどの方法が適しているのかテストと改善を繰り返し、理想的な導線を設定しましょう。
まとめ:オウンドメディアとホームページの違いを理解し使い分けよう
今回はオウンドメディアとホームページの違いについて解説をしてきましたが、この2つの最大の違いは目的です。
オウンドメディアは情報をユーザーにとって有益な情報を配信して「集客」をし、ホームページなどのゴールへ到達させることですが、ホームページはより詳しい自社の情報を知ってもらい、問い合わせや購入に至らせる「セールス」がゴールになります。
そのため、オウンドメディアを制作する際は目的やコンセプトを事前に決めなければならず、ユーザーが興味を持ちそうな事柄をリサーチして、検索キーワードを見つけ、それに合わせたコンテンツを制作しなければいけません。
それぞれ目的は違いますが、どちらも会社を経営していく上で欠かせない媒体なので、用途に応じた使い分けをして成果を上げましょう。
この記事のおさらいポイント
・ホームページは商品や事業内容など詳しい会社情報を掲載し問い合わせや購入に繋げる媒体
・2つの違いはオウンドメディアが「集客」、ホームページが「セールス」を目的とする点
・ブログは日常の出来事、オウンドメディアはユーザーの役に立つ情報を配信する
・オウンドメディアは広告の衰退や検索アルゴリズムの変化、資産化ができるなどの理由で注目されている
・オウンドメディアは目的を決め、ユーザーが検索しそうなキーワードを元に制作していく
オウンドメディアはSEOが重要で、上位表示されなければコンテンツを配信しても意味がありません。我々は自社でもオウンドメディアを運用することでそのノウハウを蓄積し、SEOに強いオウンドメディアの戦略から運用まで提案できますので、お気軽にご相談ください!






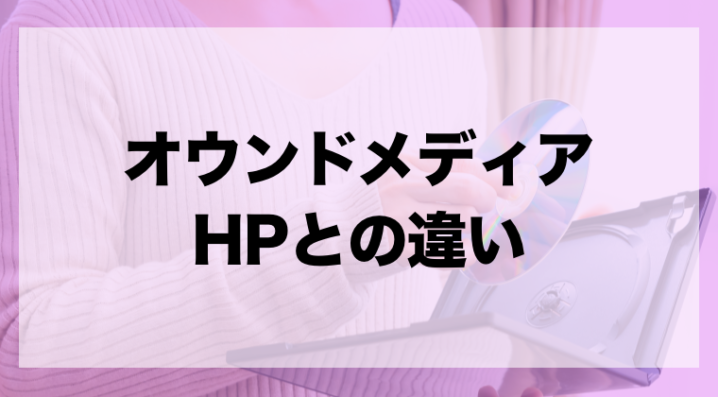
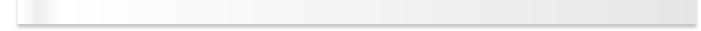
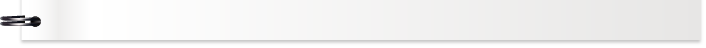
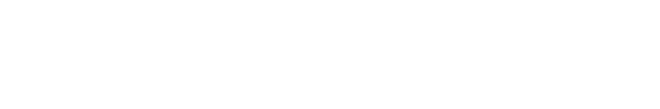
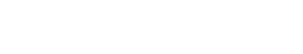

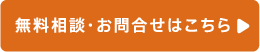

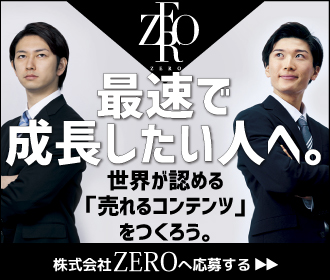
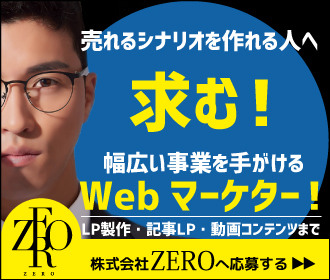
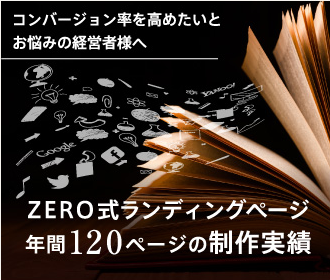

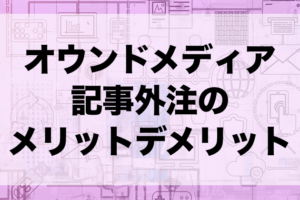
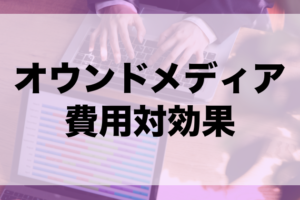
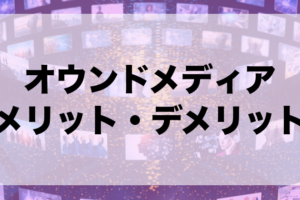
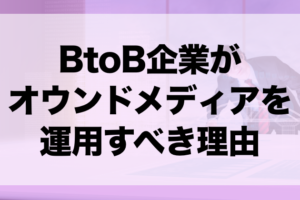
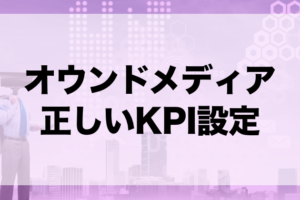
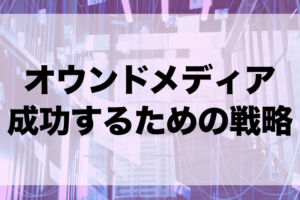
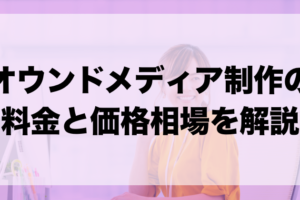
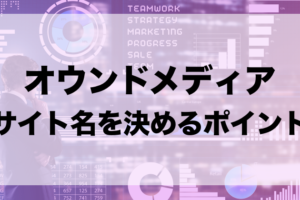
を作る方法|注意点やツールも紹介-300x200.png)
は?|具体的な数字を公開-300x200.png)